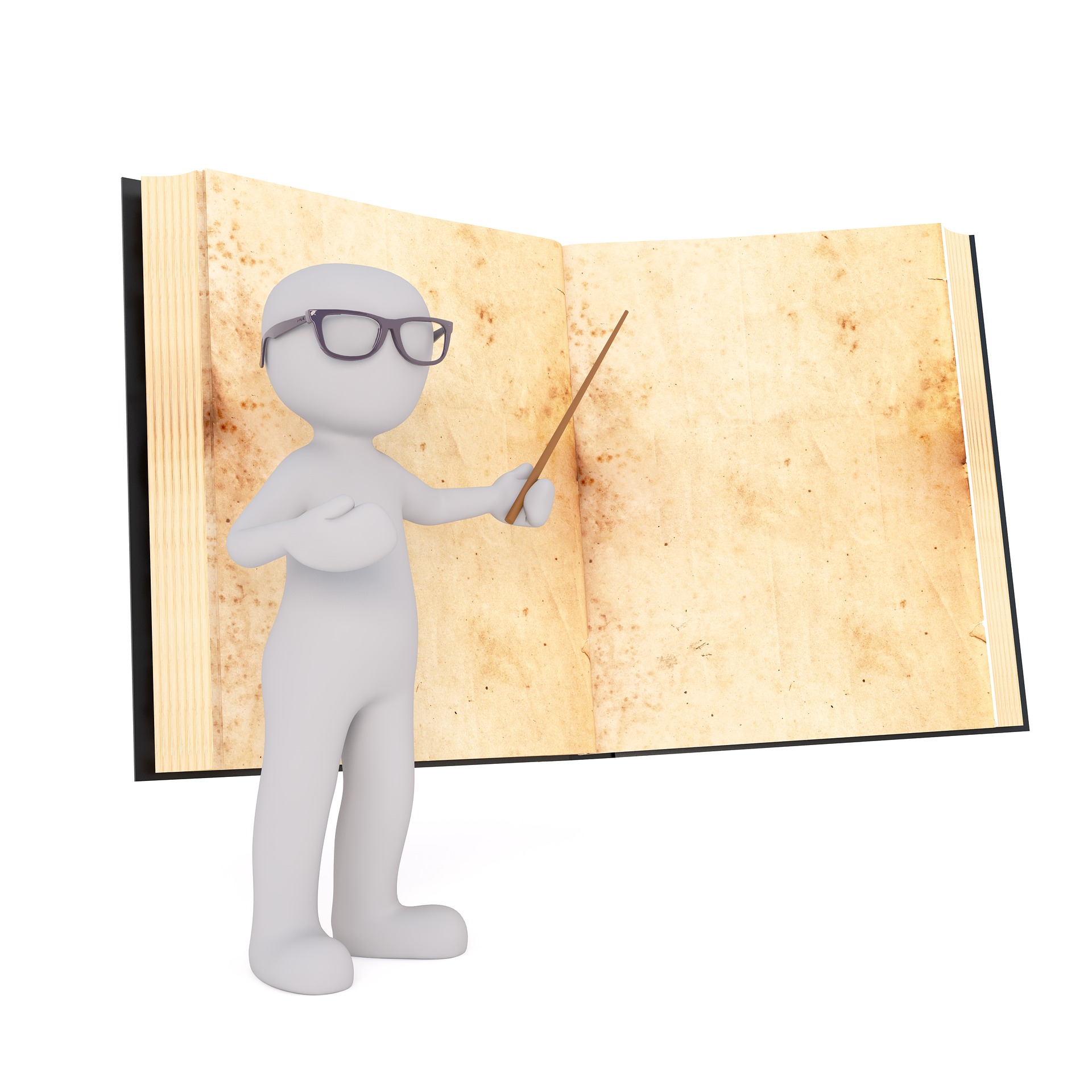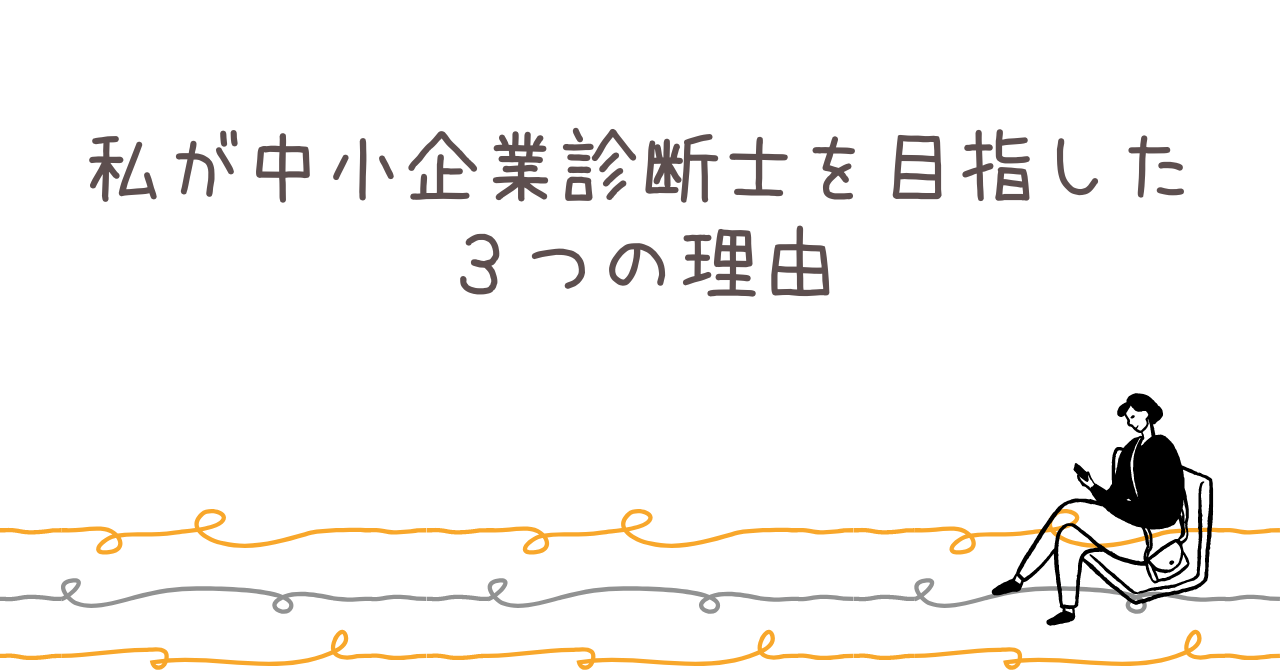家業を継ぐと決めていたけど、やっぱり悩んだ~30代後継者が考えたこと、選んだ道、そして今思うこと~

こんにちは、そうたろうです。
「家業を継ぐ」って、とても悩ましい選択だと思います。
私自身、小さなガソリンスタンドの一人息子として育ち、「いずれは継ぐんだろうな」と漠然と思っていました。
けれど、いざそのタイミングが近づいてきたとき、簡単には決められませんでした。
継がない人生もある。継ぐからこそ味わう苦労もある。
本当にこれでいいのか。迷いながらも選んだ道の先に、今の自分があります。
この記事では、私が家業を継ぐまでの葛藤と、その後に見つけた気づきについて、少しお話ししてみたいと思います。
継ぐつもりでいた背景
私の実家はガソリンスタンドを営んでいる。曾祖父と祖父が立ち上げたこの会社を、祖父が二代目、父が三代目として継ぎ、現在私が四代目にあたる。
敷地内には、ガソリンスタンドに隣接して二棟の家が建っており、一方には私と両親、もう一方には祖父母と曾祖母が暮らしていた。生活の場と仕事の場がひとつの空間にあった。
家に帰るには、いつもガソリンスタンドを横切る。それは特別なことではなく、幼い頃の私にとっては当たり前の風景だった。父も祖父も毎日スタンドに立ち、制服姿で働いていた。とくに祖父に関しては、制服以外の姿をほとんど見たことがない。それほどに、仕事と日常が一体化していた。
祖父は、生涯現役の人だった。85歳まで現場に立ち、引退してからしばらくして他界した。毎朝、私が登校するのを祖父母が見送ってくれていた。制服姿で見送ってくれる祖父の姿は、今も記憶に残っている。
祖父はよく「ぼちぼちやれよ」と言ってくれた。穏やかな言葉遣いの裏に、強い意志がにじんでいたと思う。「やってればいいんだ(続けていればいいんだ)」という言葉もよく口にしていた。祖父は自分に厳しい人だった。だからこそ、他人に優しくできたのだと、今になって感じている。
父もまた、毎日変わらず働いていた。お客様一人ひとりに親身に接し、誠実に仕事をしていた。トラブルがあっても慌てず、決して投げ出さない。背中で教える、というのはこういうことなのかもしれないと、今振り返って思う。
子どもの頃の私は、祖父や父の姿を見て、「かっこいいな」と感じていた。誰かから「継げ」と言われたわけではないけれど、一人っ子だったこともあり、「自分が継ぐんだろうな」と自然に思っていた。
ただ、それはいつしか「本当に自分は継ぐのか?」という問いに変わっていった。中学から慶應に進学し、高校、大学と進んでいく中で、周囲には大企業の御曹司やエリートサラリーマン家庭の友人が多く、自分の家業が“ちょっと珍しい存在”に見えることもあった。
とはいえ、家業に対してネガティブな感情を持っていたわけではない。ただ、当時の私は自然な流れのように、周囲と同じように就職活動を始め、そのまま大手保険会社に入社した。
大企業での7年間は、私にとって大きな学びの時間だった。最初は損害サービス部門に配属され、自動車事故の示談交渉、火災保険の査定、代理店研修の講師などを経験した。その後は、担当者12名を束ねるチームマネージャーも務め、組織運営や教育、労働環境の整備などにも関わった。事故という非日常の中で、被害者・加害者・保険会社それぞれの立場を考えながら、“最も納得感のある着地”を目指す交渉の日々は、私の価値観に大きく影響を与えた。
損害保険という仕事は、「人と物の損失に値段をつける仕事」だ。無形のものを数値化し、納得を引き出す。数字と心のバランスを取るという意味では、今の家業や診断士の仕事にも通じる部分があると思う。
そのようにして社会人としてのキャリアを築きながらも、心のどこかではずっと気にかかっていたことがある。──もし自分が継がなければ、このガソリンスタンドはなくなってしまうのではないか。
大きな会社ではない。設備も最新というわけではない。でも、ここは私を育ててくれた場所だ。曾祖父、祖父、父と続いてきた営みが、ここには詰まっている。その流れが、自分の代で止まってしまうことに、強い違和感と寂しさがあった。誰かに言われたわけではなく、心の奥で「やはり繋いでいきたい」と思っていた。
それでも揺れた20代
会社員として働く日々の中で、私はふとした瞬間に、ある感覚を抱くようになった。
どれだけ忙しくても、どれだけ重要な案件を任されても、自分がいなくても仕事は進んでいく。誰かが代わりに対応し、業務は滞ることなく回る。それが組織で働くということだと、頭では理解していた。
でも、どこかで「自分がそこにいる意味って何だろう」と考えてしまう。自分でなくてもいい、自分じゃなくても問題ない、そんな状況に対して、ほんの少しの寂しさがあった。
一方で、実家のガソリンスタンドには、もちろん従業員もいる。でも、“この場所を最終的に背負っているのは誰か”と考えたとき、そこには祖父と父の姿しか思い浮かばなかった。現場を支える人はいても、経営者としての責任と覚悟を持って立ち続けてきた人は、他にはいない。私が継がなければ、その背中は誰にも受け継がれないまま、止まってしまうかもしれない。そんなふうに思うようになった。
もちろん、会社員としての仕事にもやりがいはあった。全国を転勤し、希望すれば海外赴任の道も開かれていたし、大手企業の社員としての安定感や信用は大きな魅力だった。「このままここでキャリアを築いていくのもいいかもしれない」と思ったことも、一度や二度ではなかった。
そのなかで、祖父が仕事中に転倒して入院したという知らせが届いた。大事には至らなかったものの、それを機に祖父は現場を引退した。「ああ、本当にバトンが渡されるんだ」と、急に現実が目の前にやってきたような感覚だった。
実家に帰るたびに感じる、あの変わらない風景。父がいつものようにスタンドに立ち、同じお客様が訪れ、地元の空気の中で日常と共に仕事が進んでいく。私はその風景が、かけがえのないものに思えて仕方がなかった。
「変わらないものを、できるだけ変えずに守りたい」
その気持ちは、少しずつ心の中で輪郭を持ちはじめていた。
もちろん、経済的にはサラリーマンのほうが安定していたし、収入面でも家業よりはるかに高かった。迷いがなかったと言えば嘘になる。けれど、数字や条件だけでは測れないものが、確かに私の中に芽生え始めていた。
家族との対話、支えときっかけ
「家業を継ごうかと思っている」──。
そう父に初めて伝えたとき、返ってきた言葉は、思っていたものと違っていた。てっきり「ようやくその気になったか」と喜ばれると思っていたのに、父は静かにこう言った。
「やめるのはもったいないよ」
そして少し間をおいて、「これからは電気の時代だし、若い人も車に乗らない。ガソリンスタンドなんて、続けても厳しいんじゃないか」と言った。
予想と反応のギャップに、正直なところ、戸惑った。
私は家業を守りたいと思っていた。ガソリンスタンドという場所は、私の中でずっと特別だった。けれど、現実を見ている父からすれば、その産業の先行きを考えると、わざわざ継ぐべきものではないと感じていたのだろう。
「5年後どうなってるかなんて、誰にもわからない」
父の口調は冷静だったけれど、その言葉は、私の中にずしりと残った。
さらに祖父の言葉も重なった。
「ガソリンスタンドはもうダメだよ」
冗談まじりにそう笑ったと聞いたとき、私は笑えなかった。自分が継ごうとしているものが、当の本人たちにすら“終わるもの”として見えているのかもしれない。その現実が、じわじわと心にのしかかってきた。
そのとき私は、「やっぱり継がない方がいいのかもしれない」と思った。
会社を辞めるリスク、失敗したときの不安、家族を巻き込むことへの責任。考え始めたらきりがなかった。気持ちはある、でも気軽には飛び込めない。そんな心の中のせめぎ合いが、しばらく続いた。
それでも、私は迷いながらも、父の言葉に含まれていた“本当の意味”を探し続けた。
父は継ぐこと自体を否定したかったわけではない。ただ、自分と同じ苦労をさせたくなかったのだと思う。ガソリンスタンドは決して楽な仕事ではない。将来性も、収入も、時代の流れと逆行している部分がある。だからこそ、「本当に覚悟はあるのか?」と問われていたのかもしれない。
私は考えた。
──もし今、入らなければ。
このまま勤めを続けて、気づいたら父が引退するタイミングを迎えていたら。
そのときにはもう、遅いのではないか。
今、現場に入って、実態を見て、父と一緒に考えながら手を打たなければ。今しかない。
私の考えは、ようやく定まった。
「家業を残すだけじゃなくて、新しい柱をつくりたい。そのために、今、現場に入りたい」
そう伝えると、父は驚いたようだった。でも、最後にはうなずいてくれた。
そしてもう一人、大切な人がいた。妻だ。
当時、長女は2歳、そして妻は次女を妊娠中だった。
サラリーマンの安定を手放すことは、当然ながら大きな不安をもたらす。収入が不安定になること、土日や祝日に休めないこと、子育ての負担がどう変わるのか……。妻は最初、明確に反対だった。
「なんで今なの?」
その言葉に、私は返す言葉を一瞬失った。
けれど、結婚前から「いずれ家業を継ぐかもしれない」と話していたこと、そしてその覚悟が今になって本物になったことを、私は丁寧に伝えた。
妻は、不安な表情のまま、静かに話を聞いてくれた。
すぐに賛成はしてくれなかった。でも、最後には「わかったよ」と言ってくれた。
その一言には、心から感謝している。今、こうして家業に携わることができているのは、あのとき理解しようとしてくれた妻の支えがあってこそだと思う。
誰に背中を押されるでもなく、誰かに無理に止められるわけでもなかった。
けれど、「継ぐ」と決めるまでの時間は、自分の中で何度も揺れていた。
それでも、一つずつ対話を重ねて、思いを言葉にしていったことで、ようやく心が定まっていった気がする。
覚悟は、誰かに押しつけられて持つものではない。
対話を通じて、自分の中で自然に育っていくものなのだと、あのとき強く感じた。
大きな変化と新たな挑戦
家業に入ってから、まず感じたのは、“自由”だと思っていたものの重さだった。
大企業にいたころは、有給休暇が制度として守られていて、給与も毎月決まった額が振り込まれていた。昇給も、評価制度も、ある程度の予測ができたし、子どもが熱を出したときなどには休みやすい環境が整っていた。
それが家業に入った瞬間、すべてが“自分の判断と責任”になった。休みを取るという行動ひとつ取っても、自分の代わりがいない。しかも当時は、妻の出産も控え、上の子もまだ小さかった。現場を離れる不安と家庭の両立の狭間で、何が正しいのか分からなくなることもあった。
さらに、法人顧客の廃業などにより売上が落ちたとき、自分の給料を一定でもらっていていいのかと悩んだ。大企業にいたときは、売上の増減と自分の生活は切り離されていた。けれど、ここではすべてがつながっている。責任の矢印が、自分にまっすぐ向いていることを日々感じた。
そしてもうひとつ、大きなギャップは「経営」そのものに対する自分の無知だった。
7年間のサラリーマン経験で、社会人としての基本的なスキルや対応力は身につけてきたつもりだった。けれど、いざ家業を継いでみると、会社をどうやって舵取りしていくか、どんな方向性を描くかという視点が、自分には決定的に足りなかったことに気づいた。
「自分は、何も知らなかったんだ」
この痛感をきっかけに、私は少しずつ学ぶ姿勢を強めていった。
そんな中で、自分なりに“何かやれることはないか”と考えながら現場に立ち続けていた頃、ある気づきがあった。当社のトイレが和式であることに、お客様が不便を感じているという声だった。特に高齢者のお客様から「足がつらい」という声があり、また、近隣にはマンションが建ち、子育て世帯の来店も増えていた。
「今どきの子どもは、和式トイレを見たこともない」
そんな話を聞き、これは改善すべきだと感じた。
そこで私は、事業再構築補助金の制度を調べ、自分で申請を行った。初めての補助金申請は手探りだったが、結果的に採択され、店舗のトイレを洋式に改修することができた。改修後、常連のお客様から「使いやすくなったよ、ありがとう」と言ってもらえたとき、これまでにない達成感があった。
父からも、「入ってくれてよかった」と言われた。この言葉は、胸に残っている。
この経験を通じて私は、「中小企業の“こうしたい”という想いを、事業計画や補助金を活用しながら形にしていく」という仕事の存在を知った。事業再構築補助金をはじめ、国のさまざまな支援制度の中で、専門家が経営計画の策定や財務面の整理を通じて伴走する——そんな支援の在り方に、強い魅力を感じた。
同時に、自分自身が経営に関する体系的な知識を持っていないことも、改めて痛感した。だからこそ私は、「中小企業診断士」という国家資格に挑戦することを決めた。
中小企業診断士の仕事は、設備を持たず、人も雇わず、自分の身ひとつでできる。極力レバレッジをかけず、等身大で経営に寄り添っていくそのスタイルは、まさに“家業”の在り方とも重なる部分があった。これならば、自分の価値を育てながら、無理なく広げていける。そう確信できた。
今では、地域の中小企業に対してWebマーケティングや補助金活用のアドバイスを行ったり、事業計画の作成支援に関わったりと、少しずつ「外に開かれた自分のビジネス」として活動を始めている。家業を支える軸を持ちつつ、地域とつながるもう一つの仕事。それが、私にとっての新しい挑戦のかたちだ。
家業と社業
経営の勉強を進める中で、経営とは「何を目指すのか」を定めることなんだと、強く感じるようになった。
その中で、家業と社業の違いについて考えた。
同じ“経営”という言葉でも、家業と社業では向いている方向がまるで違う。私は今、自分たちの立ち位置を見つめ直す中で、あらためてその違いを意識している。
社業の本質は、拡大だと思う。
できるだけ多くの資金を調達し、人を雇い、設備投資を行い、店舗を増やしていく。そして売上や利益を伸ばし、最終的には上場や売却といった出口を見据えていく。そこでは自己資本に対して最大限のレバレッジをかけ、経営の規模を拡大し続けることが求められる。従業員数も、自己資本も、何倍にも膨らませていくことで利益を最大化する。
いわば、社業とはハイリスク・ハイリターンの世界だ。
一方で、家業はそれとは正反対の性質を持っていると感じている。
無理な拡大はせず、過度な借入も避け、できるだけ自己資本で、家族の手の届く範囲で経営していく。人手も最小限で、時間をかけて積み上げていく。そこにあるのは、リターンよりも“継続”の重視だ。ゴールというよりは、「繋ぎ続ける」こと自体が目的になっている。
私の父も、「過度なリスクは取るな」とよく言う。
それは裏返せば、「何かあったときに守り切れない規模にはするな」ということでもある。長く続けるというのは、ただ耐えるということではない。変化に対応しながら、危機のときにも無理をせず、少しずつでも成長していくバランスが必要だ。
私は家業の中で、「変わることは、変えたくないものを守る手段だ」と考えている。
現状維持は衰退の始まりだ。ガソリンの需要が減っていくことは明らかであり、若者の車離れも加速している。そんな中で、ただ同じことを繰り返していたら、いずれ“継続”すらできなくなる。だからこそ、どこかで新しい事業や仕組みを考え、少しずつでも成長の糸口をつかんでいくことが必要だと思っている。
変えるべきところは変える。でも、大事にしたいものは守る。
私たちのガソリンスタンドは、地域のお客様に支えられてきた。今でも「昔から知ってるよ」「おじいちゃんの頃から来てるよ」と言ってくださるお客様が多い。そんな方々に、「後継者が入ったから、もう安心だね」と言われたとき、私はこの仕事を選んでよかったと心から思った。
会社として目指す姿も、そこにある。
急成長する会社ではなくてもいい。地元で、「あそこに行けば安心だ」「ちゃんと対応してくれる」と思ってもらえる場所でありたい。地域の中で、なくてはならない存在になること。それが、家業としての理想形だと思う。
そして、家族の中での自分の役割についても、最近よく考えるようになった。
私は父と祖父の背中を見て育った。彼らが何を語ったかよりも、どう働いていたか、どんなふうに人と接していたか、それが自然と自分の中に染み込んでいた。
だからこそ、私も、自分の子どもに対して何かを“教えよう”とは思っていない。
もちろん、将来、子どもに会社を継いでもらうことを前提にはしていない。
けれど、何かを真剣に続けていくこと、家族や地域との関係を大切にしていくこと。そんな背中を見せていくことで、子どもが自分自身の価値観を持ち、自分の進む道を考えてくれたら、それが一番の願いだ。
悩んだからこそ、今がある
もし、あのとき家業を継がない選択をしていたら──
きっと今頃、どこかの地方都市、あるいは海外で、妻と子どもと一緒に暮らしていたのかもしれない。
大きな会社の中で、年次を重ねながら、少しずつ責任ある立場になっていたはずだ。そこには一定の充実感もあっただろうし、収入面の安定もあったと思う。
サラリーマンとしての人生を否定するつもりはまったくないし、実際に私自身、そこで得た経験や仲間はかけがえのないものだった。
ただ、その選択をしていたら、父や祖父のように“背中で語る”ということは、もしかしたら学べなかったかもしれない。
小さな頃から、毎日制服を着てスタンドに立つ祖父の姿が、当たり前の風景だった。
いつもスタンドでお客様と向き合い、親身に接するその姿が、私には誇らしく映っていた。
父もまた、そうやって背中を見せてきた人だった。家業というのは、そういう“覚悟”を日々の仕事に込めながら、誰に語るでもなく、でも確かに伝えていくものなんだと思う。
もしも今、家業に戻らずにいたら。
いずれ父が高齢になり、仕事ができなくなったとき、会社を畳むという判断を迫られていたかもしれない。
その時になって、「やっぱり戻っておけばよかった」と後悔する可能性は、きっとゼロではなかったと思う。
家業に戻ってきた今でも、これが正解だったかどうかは、やっぱり分からない。
というよりも、正解や不正解なんて、そもそもないのかもしれない。
人生において、「選ばなかった道」が正解だったかもしれないと思うことは誰にでもある。けれど私は、自分が選んだ道を、できるだけ正解に近づけたいと思っている。
実際、今の私は家業に入って、いろいろな壁にぶつかりながらも、ひとつずつ乗り越えてきた。
補助金を使ってトイレを改修したり、中小企業診断士の資格を取得して支援の仕事を始めたり。
現場の声を聞き、考え、行動し、その結果としてお客様や家族から「ありがとう」と言ってもらえる。
そんな毎日は、決して楽ではないけれど、確かにやりがいを感じている。
これから先も、私はまだまだ迷うことがあるだろうし、失敗もすると思う。
けれど、祖父や父がそうしてきたように、少しずつでも会社を前に進めていきたい。そしていつか、自分の子どもが、私の背中を見て何かを感じてくれる日が来たら、それが一番嬉しい。
悩んだからこそ、今がある。
そう胸を張って言えるように、これからも毎日を積み重ねていこうと思っている。
おわりに
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
私はずっと、家業を継ぐことは「自然な流れ」だと思っていました。けれど、いざその瞬間が近づくと、自分の中には想像以上の迷いや葛藤がありました。
周囲の友人たちはそれぞれのキャリアを歩んでいて、サラリーマンとしての安定や選択肢も、決して悪いものではない。そんな中で、「自分がなぜ継ぐのか」という問いに何度も立ち返りながら、ここまで来ました。
この本は、そんな自分自身の「悩んだ時間」を記録しておきたいという思いから始まりました。
そしてそれが、今まさに同じように悩んでいる誰かにとって、少しでも参考になればという願いも込めています。
家業を継ぐことに正解はないと思います。
継がなかったとしても、その人なりの人生があり、そこに誇りを持つことは何もおかしいことではありません。
ただ、私は「継ぐ」と決めたことで、自分の中に新しい視点と責任感が芽生えたのは確かです。
家業というのは、仕事であると同時に、家族であり、暮らしでもあります。
だからこそ複雑で、だからこそ面白くて、続ける意味がある。
自分の判断で進むからこそ、すべてが自分に返ってくる。その緊張感のなかにこそ、やりがいがあるのだと思います。
もしあなたが、家業を継ぐかどうかで迷っているなら、私の話が一つのヒントになれば嬉しいです。
迷っていいし、悩んでいい。
その時間は、きっと無駄にはなりません。
そしていつか、自分の選んだ道を、少しでも「よかった」と思える日が来ることを、心から願っています。