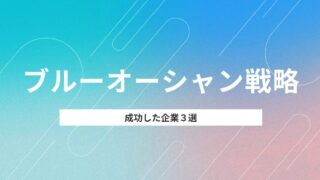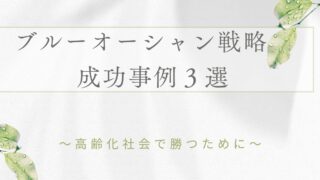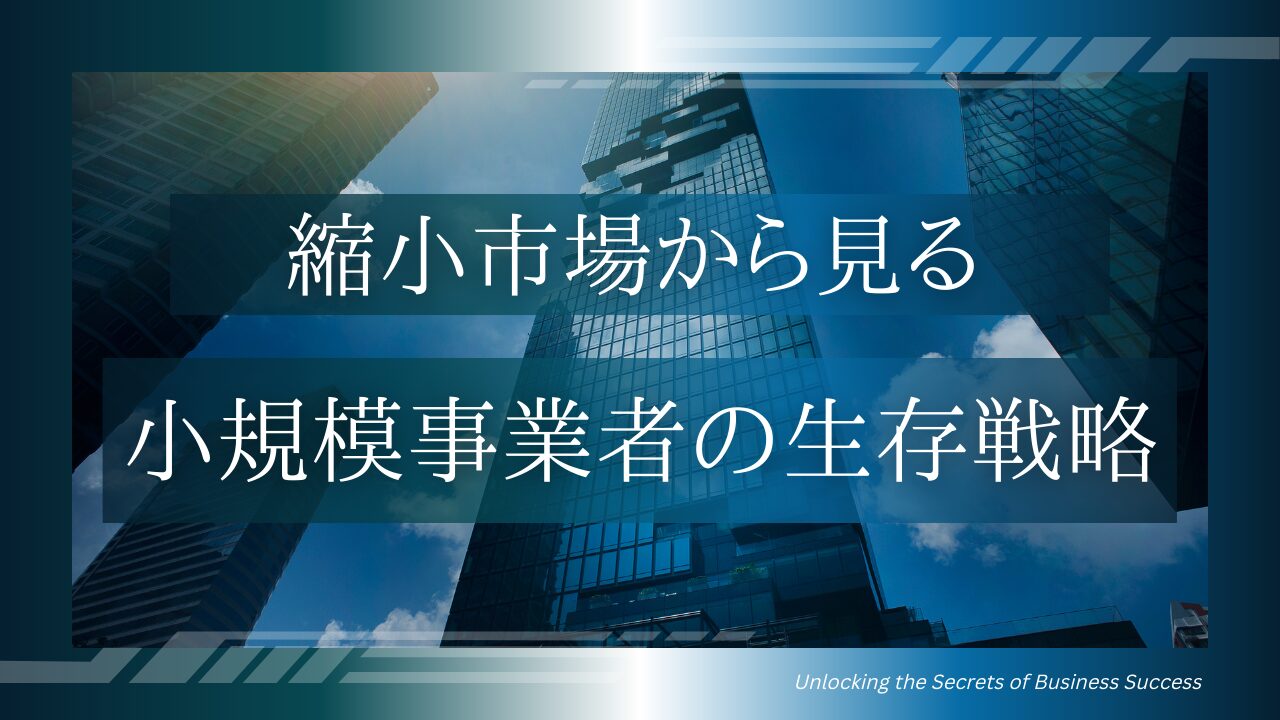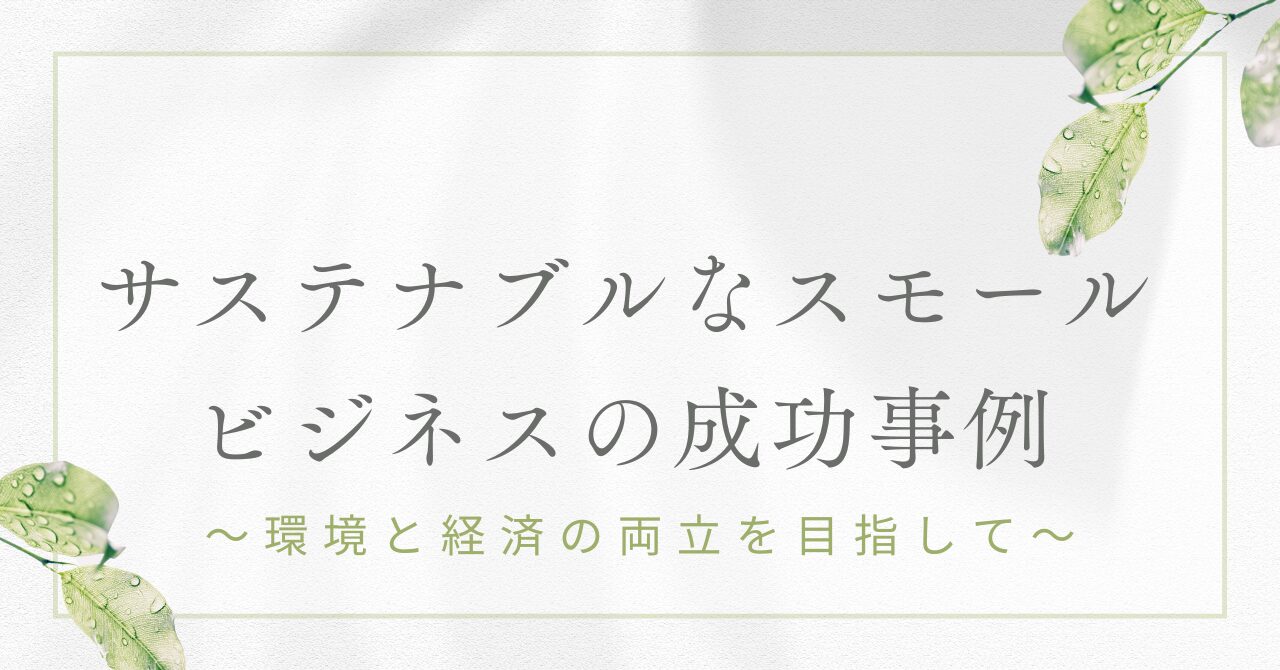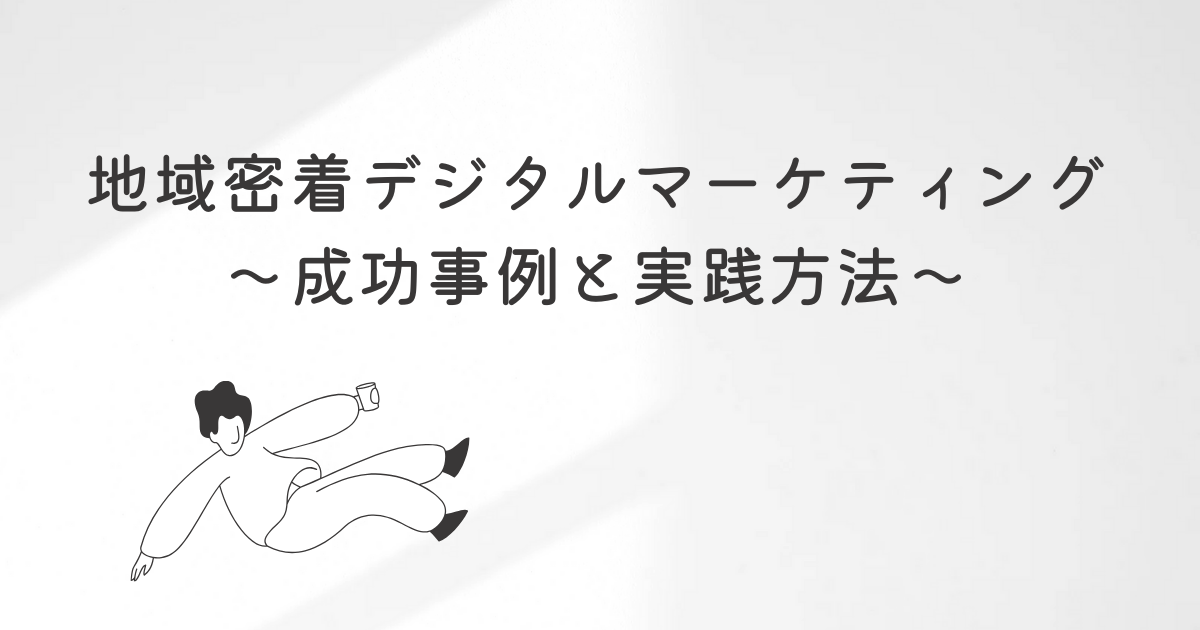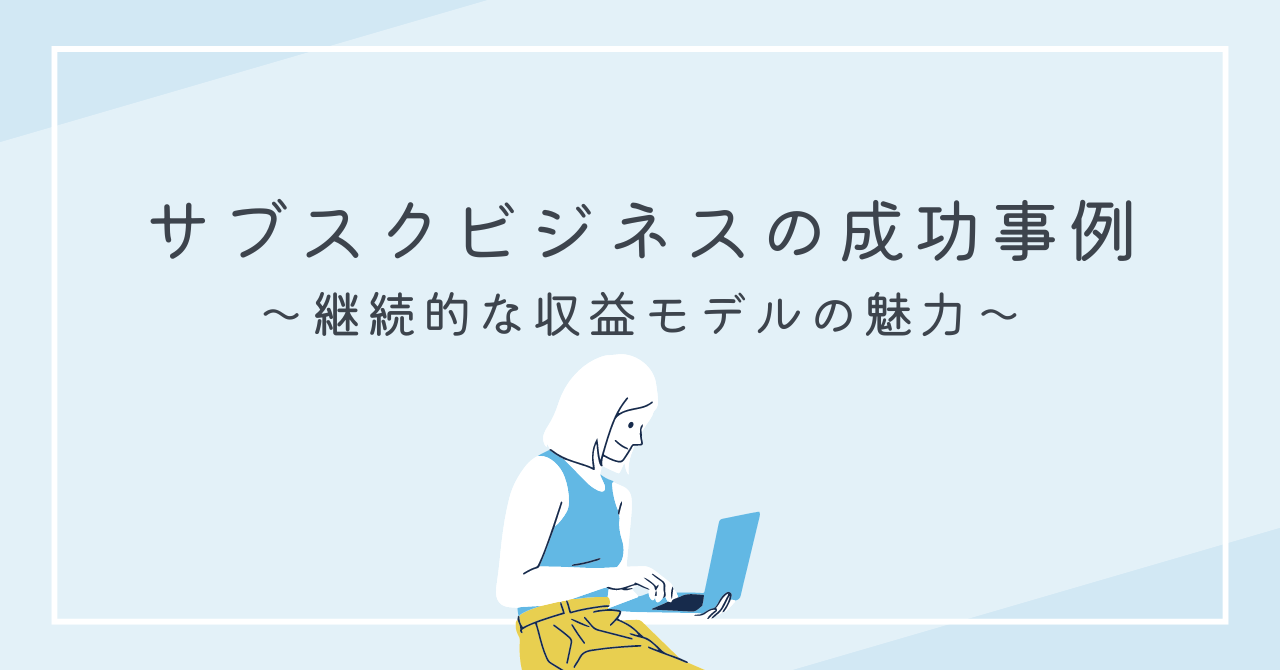個人で実践するブルーオーシャン戦略~フリーランス・副業でも競争しない働き方~

こんにちは、そうたろうです。
今日は「個人が実践するブルーオーシャン戦略」というテーマでお話しします。
これまでこのブログでは、中小企業や特定業界、高齢化社会などを題材にブルーオーシャン戦略の考え方や活用法を紹介してきましたが、今回は「個人」にフォーカスしてみたいと思います。
副業や独立、フリーランスといった選択肢が現実的になった今、企業ではなく“個人”がプレイヤーとして市場に出ていくことが当たり前の時代になっています。
そんな中で、競争から一歩離れた場所で自分の市場を築いていく「ブルーオーシャン戦略」は、まさに今の時代の働き方と相性が良いのではないかと思います。
私自身もまだ模索中の立場ですが、中小企業診断士と宅建士の資格、そして家業の不動産業の経験を活かして「事業承継×不動産×経営支援」のような掛け合わせに可能性を感じています。
この記事では、そうした視点をもとに、個人がブルーオーシャンをどう見つけ、どう形にしていくかについて考えてみたいと思います。
ブルーオーシャン戦略は以下の記事で解説しています。
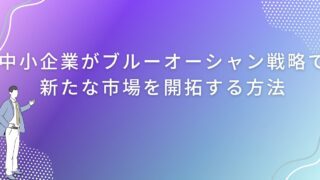
個人がブルーオーシャン戦略を考えるべき理由
近年のフリーランス人口は急増しています。
たとえばランサーズの「フリーランス実態調査2023」によると、広義のフリーランス人口は現在1577万人に達し、就業者全体の約24%を占めています。
これだけ多くの人が“個人で稼ぐ”という選択をしている一方で、SNSを使えば誰でも発信できる今、同じようなサービスや肩書きの人が増えすぎて、競争はますます激しくなっています。
たとえば、
- 「ライター」は無数にいる
- 「中小企業診断士」は全国に3万人超
- 「不動産の資格者」も大量にいる
つまり、どの市場もすでに“レッドオーシャン”化しています。
そんな中で、他人と似たようなポジションで勝負しても、価格競争や消耗戦になるのがオチです。だからこそ、「自分だけの土俵=ブルーオーシャン」を定義する必要があるのです。
自分の履歴書を“戦略化”するという発想
ブルーオーシャン戦略の本質は、「競争を避けて、独自の価値で勝負する」ことにあります。
そして、個人がそれを実現するための第一歩は、自分自身の経歴やスキルを組み合わせて“自分だけの市場”をつくることです。
たとえば私自身は、以下のような要素を持っています。
- 中小企業診断士
- 宅建士
- 家業(不動産業)に関与
- 損保業界での実務経験
- 地方在住(東京圏ではない)
この時点で、診断士として“競争力がある”わけではありません。でも、これらを掛け合わせることで、
「地方の中小企業を対象に、事業承継や不動産資産の活用支援、補助金を含む経営コンサルを行う人」
というポジションをとれば、「他にいない存在」になれる可能性が出てきます。
同じように、以下のような掛け合わせも考えられます。
- 元看護師×メンタルヘルス×キャリア支援
- 海外駐在経験×語学×日本企業の海外進出支援
- 子育て経験×IT×主婦層向けデジタル教育
つまり、“どんな履歴も戦略になる”のがブルーオーシャン思考です。
STP分析で個人市場を設計する
「なんとなく差別化しよう」ではなく、しっかり戦略として立てるには、フレームワークの活用も有効です。
ここではSTP分析(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)を紹介します。
セグメンテーション:
市場を細かく分けて、自分のスキルが役立ちそうな小さな“島”を見つけます。
例:「地方中小企業」「高齢者向け」「一次産業従事者」など
ターゲティング:
どの“島”を狙うかを決めます。
例:「地方の事業承継を考えている経営者」
ポジショニング:
その島で、自分がどんな役割を果たすのか、どんな立場に立つのかを決めます。
例:「資産の見直しから不動産売却、補助金活用までワンストップで支援する人」
このように、フレームワークを使って戦略設計することで、再現性のある動きができます。
“ズレ”を強みに変えるという視点:成田悠輔氏に学ぶ
成田悠輔さんは、「ズレていることがむしろ武器になる」とよく仰っています。
現代は「普通でいること」の価値が下がり、「違和感を出せること」が個性として評価される時代です。
私自身も診断士として、「標準的で真面目な専門家」になるより、「ちょっと変な視点で現場に寄り添える人」を目指す方が合っていると思うようになりました。
「誰と同じか」よりも、「誰とも違うか」
この視点を持てるかどうかが、個人のブルーオーシャン構築には大きな違いを生みます。
成功事例:育児×漫画×SNSで市場を作った主婦
たとえば、以下のような事例があります。
30代の主婦Aさんは、育児中の経験をもとに「子どもの発達×知育×親のメンタルケア」をテーマに、Instagramで漫画発信を開始。
自ら描いた“育児のリアル”を通じて、同じ悩みを持つフォロワーとつながり、やがてオンライン講座や教材販売を始めるようになりました。
最初から市場があったわけではなく、「自分が欲しかったもの」を自分で形にして、それに共感する人が集まったことで、結果的に“市場になった”のです。
まとめ:ブルーオーシャンは「定義」するもの
ブルーオーシャンは、どこかに落ちているものではありません。
自分で定義し、自分の手で広げていくものです。
まとめると、個人が実践するブルーオーシャン戦略では以下が大切です。
- 自分の経歴・スキルを掛け合わせる
- セグメント・ターゲット・ポジションを明確にする
- 競争を避け、自分らしい違和感を打ち出す
- 小さくても“自分だけの市場”を定義する
そして何より、自分の履歴そのものを「資産」として見直すこと。
誰にも真似できないのは、あなたの人生そのものです。
私自身、「事業承継 × 宅建士 × 診断士」という軸でブルーオーシャンを模索している最中です。
これから形になっていく過程も、引き続きこのブログで発信していけたらと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。