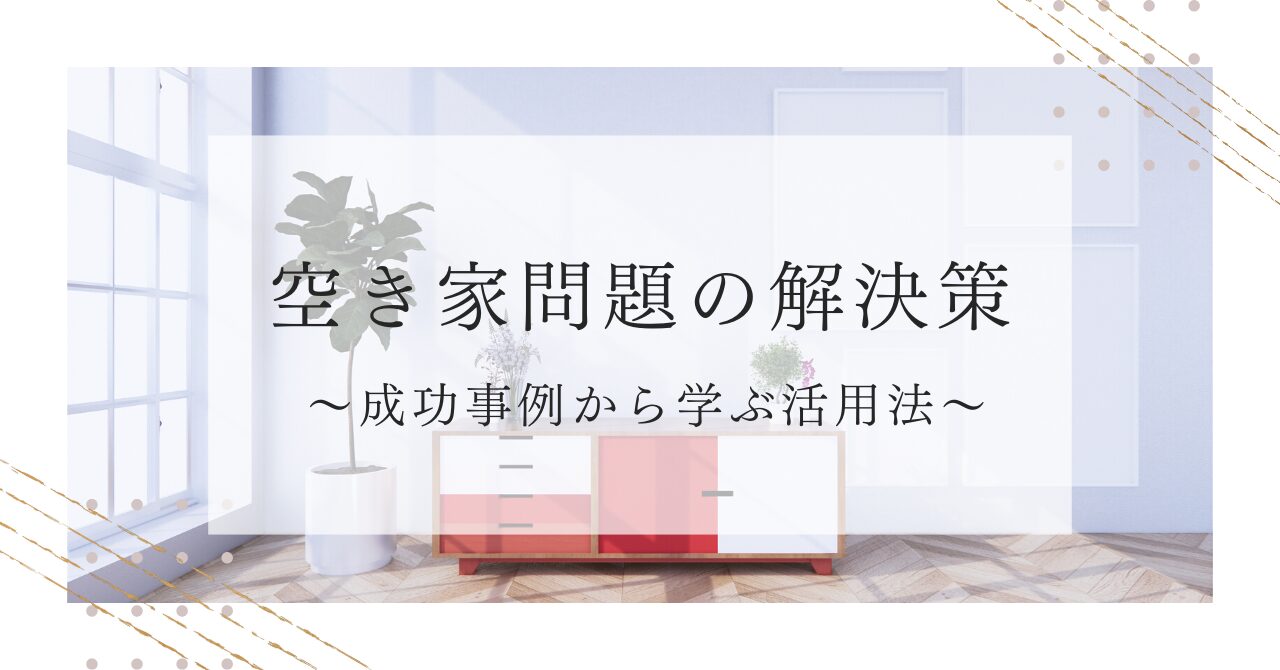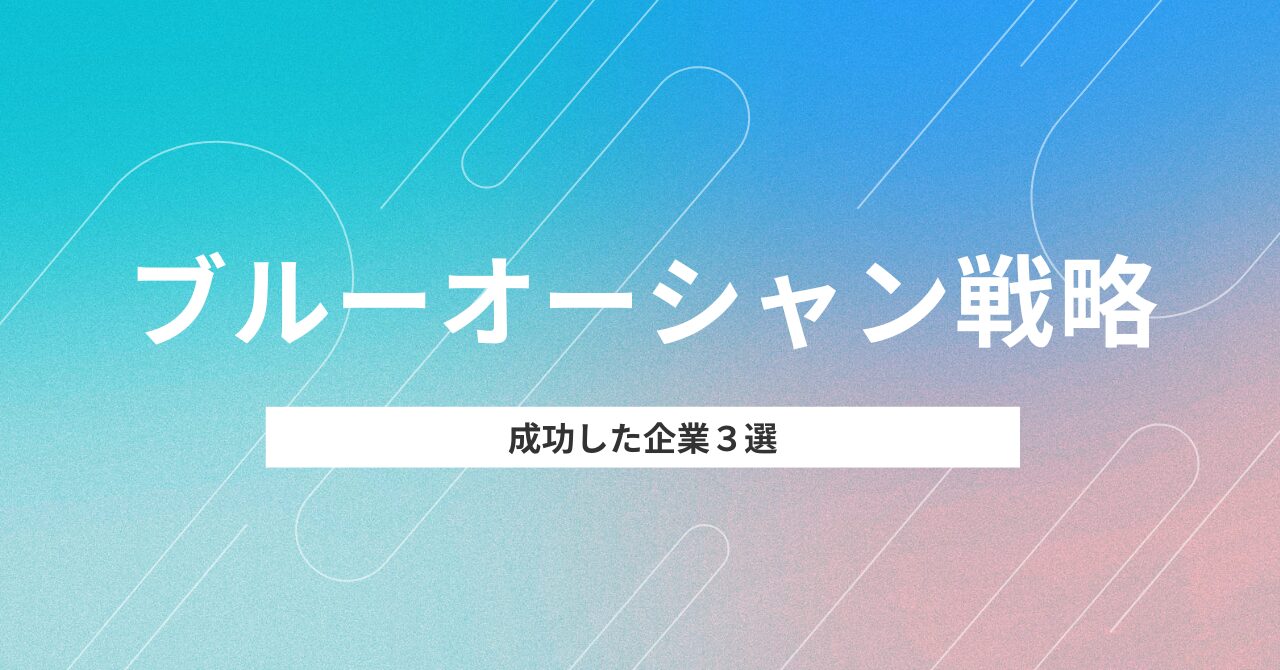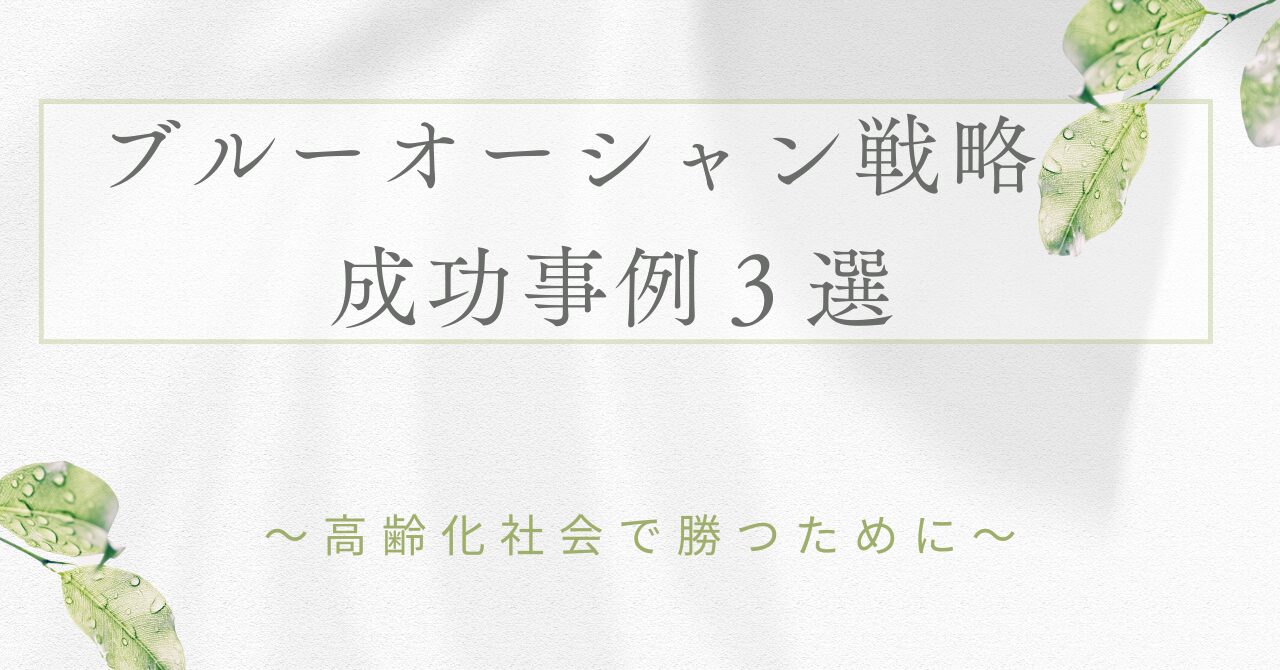ガソリン価格推移20年を分析!燃費改善で変わる1kmコストと業界の未来
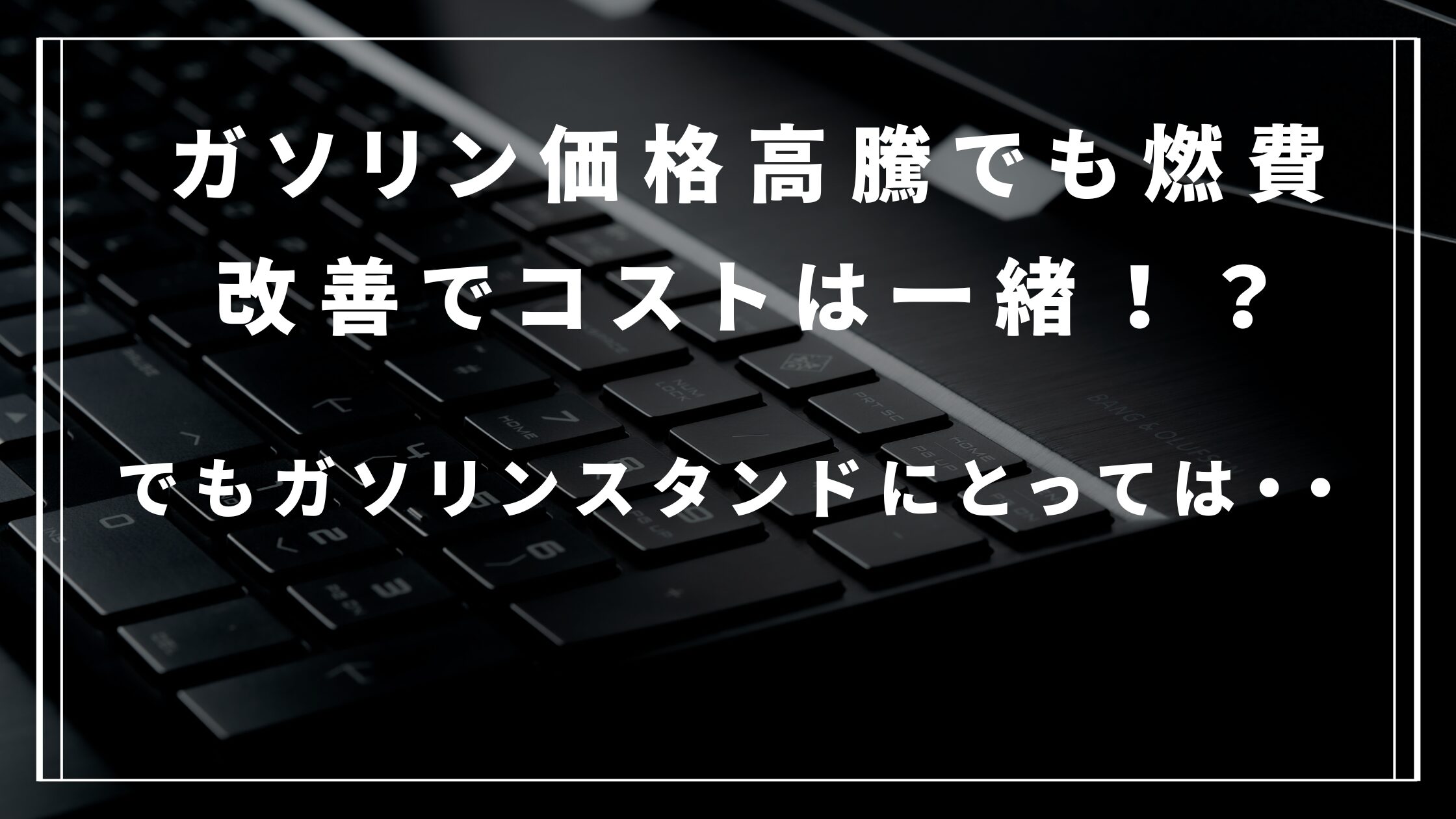
こんにちは、そうたろうです。
私は創業60年を迎えた家業のガソリンスタンド後継ぎ&中小企業診断士(30代前半)です。
今回はガソリンスタンド経営者や小規模事業者の方向けに、過去20年のガソリン価格推移と燃費データの変化を国際・国内情勢と絡めて分析し、1kmあたりの燃料コストがどう変わってきたのかを見てみたいと思います。
また、中東・ウクライナ情勢による原油供給への影響やホルムズ海峡封鎖のリスク、日本政府のガソリン補助政策の推移について整理します。
さらに、ガソリンスタンド業界が直面している構造変化と、小規模事業者向けの補助金(小規模事業者持続化補助金)の活用情報も紹介します。
最後に、業界の今後と経営者として取り得る選択肢について考えてみましょう。
それでは早速、本題に入ります。
私がサラリーマンを辞めてガソリンスタンドを継いだ理由は以下記事に記載しています。

中東・ウクライナ情勢がガソリン価格に与える影響
まず、ガソリン価格を語る上で欠かせない国際情勢の影響から見ていきましょう。ガソリンの原料である原油価格は、中東やロシアなど産油地域の情勢によって大きく左右されます。
ここ20年を振り返っても、中東の緊張やロシアによる戦争が世界の原油供給不安を招き、価格が急騰する場面がありました。
中東情勢:イスラエルとイランの緊張
中東情勢が原油市場のリスク要因となっています。例えばつい先日(2025年6月)、イスラエルがイランへの攻撃を行い、中東で戦争が拡大する懸念から原油先物価格が急騰しました。
世界の原油生産の約3分の1を中東地域が占めるため、この地域の武力衝突は原油供給に直結する懸念があります。
特にイランは主要産油国の一つであり、仮にイランの原油輸出が止まれば市場への影響は甚大です。また最悪のシナリオとしてホルムズ海峡の封鎖が挙げられます。
ホルムズ海峡はペルシャ湾から原油を輸送する要衝で、世界の原油の約20%が通過するとも言われます。
専門家によれば、「イランの原油供給が完全停止しホルムズ海峡が閉鎖される最悪の事態では、原油価格が1バレル=120ドルを超える可能性」があると指摘されています。
実際ゴールドマン・サックスも、ホルムズ海峡封鎖となれば原油価格が100ドル/バレルを上回る展開もあり得ると警告しています。
幸い現時点ではそうした極端な事態には至っておらず、中東の緊張が高まっても「エネルギー価格が長期高止まりする可能性は低い」との予想もあります。
しかし地政学リスクは常に頭に入れておく必要があり、中東情勢の悪化は即座にガソリン価格にも波及し得ることを念頭に置いておきたいです。
ウクライナ情勢:ロシア産原油への制裁
次にロシアによるウクライナ侵攻がもたらした原油価格への影響です。
2022年2月に勃発したロシア・ウクライナ戦争は世界のエネルギー市場を混乱させ、直後の2022年3月に原油価格は一時1バレル=130ドルに達しました。
当時は「150ドル超えもあり得る」とまで取り沙汰されましたが、その後各国がロシア産原油の禁輸や価格上限制を実施しつつも、ロシア原油は中国・インドなど他の市場へ流れ、欧州は中東や米国産で代替する形で需給が再調整されました。
その結果、原油価格の高騰は数ヶ月で一服し、夏以降には下落に転じています。
つまり「ロシア産原油が市場から消える」との最悪の供給不安 (“ロシア・プレミアム”) は回避され、市場は意外にも早く落ち着きを取り戻したのです。
しかし一方で、ロシア産エネルギーへの依存度が高かった欧州を中心に、エネルギー価格高騰が各国経済・物価に与えた影響は大きく、日本でもその余波でガソリン価格が上昇しました。
実際、日本のレギュラーガソリン小売価格は2022年夏頃に全国平均で170円/リットル超まで急騰し、家計や物流業への負担が深刻化しました。
このため日本政府は緊急措置として後述するガソリン価格補助金制度を開始し、小売価格が急激に上がり過ぎないよう市場に介入する事態となりました。
ウクライナ戦争は「エネルギー安全保障」の重要性を改めて認識させ、日本のガソリン価格にも直接的な影響を与えた出来事でした。
ガソリン価格高騰への日本政府の対応:補助金と税制
続いて、日本国内に目を転じてガソリン価格高騰に対する政府の政策対応を見てみます。ガソリン価格は国際要因だけでなく、国内の税制や補助政策によってもコントロールされてきました。
特に近年は、ウクライナ危機以降の物価高に対応するため日本政府が異例の補助金支給策を講じています。
燃料油価格激変緩和措置(ガソリン補助金)
日本政府は2022年1月、ガソリン価格上昇による国民生活や産業への影響を緩和する目的で、石油元売各社に対する補助金支給を開始しました。
これはガソリンなど燃料油の卸売価格を人為的に引き下げ、小売価格の高騰を抑えるための措置です。
当初はコロナ禍からの経済回復を支える暫定的な措置として2022年度限り(2022年~2023年3月末)で終了予定でしたが、その後も円安やウクライナ危機に伴う物価高騰が収まらなかったため、政府は補助金制度の延長を繰り返しまし。
結果としてこの補助金には2022年からの累計で8兆円超もの巨額の財政支出が投じられており、国家的にも大きな負担となっています。
さすがに補助金を永続させるわけにはいかず、政府は2024年12月から段階的に補助額を縮小し、出口戦略を模索し始めました。
補助金の減額に伴い、足元のガソリン小売価格は再び上昇傾向にあります。実際、補助金支給額が縮小された2025年2月中旬時点でレギュラーガソリン全国平均184.5円/Lと、過去にない高値水準が続きました。
補助金が一時ゼロとなった2023年8月~9月には全国平均186円/Lに達し、統計開始以来の最高値を更新しました。
現在は10円の補助金に加え、原油価格が下がっていた影響で160円台となりましたが、先日イスラエルがイスラエルに攻撃したことより再度上昇していく見込みです。
政府は直近まで補助金措置を7度以上延長してきましたが、財政負担や市場歪みへの懸念もあり、今後は補助金に頼らない価格安定策への移行が課題となっています。
ガソリン税と「トリガー条項」
日本のガソリン小売価格には1リットル当たり約53.8円のガソリン税(揮発油税等)と2.8円の石油石炭税、さらに消費税が上乗せされています。
もともとガソリン税には道路整備財源としての暫定税率(25.1円)が長年含まれてきましたが、税制議論の中でこの暫定税率を巡る攻防が起きたことがあります。有名なのは2008年、与野党対立で一時的に暫定税率が失効し、その期間だけガソリン価格が大幅に下がったエピソードです(翌月には暫定税率が復活し元の価格に戻りました)。
また2010年には民主党政権下で、ガソリン高騰時にガソリン税(暫定税率分)を一時的に減税する仕組み「トリガー条項」が導入されました。
具体的には「レギュラーガソリンの全国平均価格が160円/Lを3ヶ月連続で超えた場合、翌月から暫定税率部分(25.1円/L)を課税停止する」という内容です。
本来であれば2022年の高騰局面で発動要件を満たしていましたが、実際にはトリガー条項は発動されませんでした。これは東日本大震災以降に同条項が凍結されているためで、政府・与党は補助金による価格抑制を優先し、減税による対応を見送った経緯があります。
2024年末には与党と一部野党の合意でガソリン税の一部(暫定税率相当分)を恒久的に廃止する方向も議論されましたが、最終的な結論は執筆時点(2025年6月)でも流動的です。
いずれにせよ、ガソリン税制は価格に大きな影響を及ぼすため、経営者として注視すべきポイントです。今後、補助金終了後にガソリン税の見直し(減税措置など)が行われるのか、それとも市場任せになるのかで、小売価格の水準感が大きく変わってくるでしょう。
ガソリン価格と燃費の20年推移:1kmあたり燃料費はどう変わった?
では、本題である過去20年のガソリン価格と燃費データの推移を具体的な数字で見てみましょう。
国際情勢や政策によってアップダウンを繰り返したガソリン価格ですが、その間に自動車の平均燃費も飛躍的に向上しています。
両者を合わせて振り返ることで、「1km走行あたりの燃料コスト」がどのように変化したかが見えてきます。
まずガソリン価格の長期的な流れを簡単にまとめます。
1990年代後半の日本ではガソリンがリッター100円前後と比較的安価で安定していました。
しかし2000年代に入ると世界的な原油需要の増加で価格は上昇基調となり、2008年夏には原油史上最高値(WTI147ドル)を背景に全国平均180円近くにまで急騰しました(当時ハイオクは一部地域で200円/L超えのスタンドもありました)。
ところが直後のリーマンショックで需要が落ち込み、2009年前半にはガソリン110円台へ急落しています。
その後2010年代前半は原油高止まりでガソリンも140~150円台が続きましたが、2014年のシェール革命による原油安で2016年3月には109円/Lと約10年ぶりの安値を記録しました。
しかし再び需給が締まると上昇に転じ、2018年には一時160円超え、概ね150円前後で推移しました。
直近の2020年代前半はコロナ禍で一時的に需要蒸発し120円割れとなった後、経済再開とウクライナ危機で再び急騰、2023年に186円/Lという過去最高値を更新しています。
一方、この20年で乗用車の平均燃費は大きく改善しました。
国土交通省と経産省の資料によれば、1997年のガソリン乗用車の平均燃費は12.4 km/Lでしたが、2016年には21.9 km/Lと約20年で平均燃費がほぼ倍増しています(※2011年度に試験方法が変わっており単純比較はできませんが、傾向として燃費は大幅向上)。
燃費向上の背景には、「アイドリングストップ機能の普及」「CVT(無段変速機)の採用拡大」「ハイブリッド車の大量導入」といった技術進歩があり、自動車メーカー各社の努力でガソリン1リットルあたりの走行距離は飛躍的に伸びました。
では、ガソリン価格と平均燃費を組み合わせると1km走行あたりの燃料コストはどう変わったでしょうか?
以下の表に、2000年代初頭から現在まで約5年おきのガソリン価格と燃費、および1kmあたりの燃料費の目安を示します(価格はレギュラー全国平均の概算、燃費は当時の新車平均値の概算です)。
過去20年のガソリン価格と平均燃費・1kmあたり燃料費の推移
| 年頃 (目安) | ガソリン価格 (円/L) | 平均燃費 (km/L) | 1kmあたり燃料費 (円/km) |
|---|---|---|---|
| 2003年頃 | 約110円/L | 約13 km/L | 約8.5円/km |
| 2008年頃 | 約180円/L | 約15 km/L | 約12.0円/km |
| 2013年頃 | 約150円/L | 約18 km/L | 約8.3円/km |
| 2018年頃 | 約150円/L | 約22 km/L | 約6.8円/km |
| 2023年頃 | 約170円/L (※最高186円) | 約23 km/L | 約7.4円/km |
※上記は概算値ですが、傾向ははっきりしています。例えば2008年はガソリン価格が非常に高騰したため、1km走行あたりの燃料コストは約12円と突出して高くなりました。
当時は平均燃費も15 km/L程度と現在より低かったため、高値のガソリンが直撃した形です。
一方、直近の2023年はガソリン価格そのものも高水準ですが、平均燃費が約23 km/Lまで向上した結果、1kmあたりコストは7~8円程度に抑えられています。
20年前(2003年頃)の約8.5円/kmと比べても同水準かむしろ低い計算になります。つまり、「ガソリン代」は上がっても「燃料費負担」は技術進歩によってある程度相殺されてきたと言えます。
ハイブリッド車の普及などで燃費が倍近く良くなった効果は大きく、ガソリンスタンド業界にとっては「燃料が売れなくなる要因」となりましたが、ユーザー側にとっては燃料コスト低減というメリットをもたらしました。
ガソリンスタンド業界への影響と構造変化
国際情勢による原油価格の乱高下や、国内政策・技術トレンドの変化は、ガソリンスタンド業界の構造にも大きな変化をもたらしています。
過去20~30年で日本全国のガソリンスタンド数は大きく減少しましたが、その背景にはいくつもの要因があります。ここでは業界動向と要因を整理し、今後の展望を考えてみます。
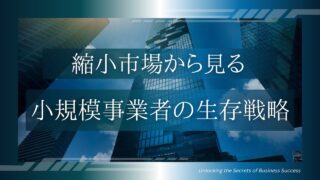
ガソリンスタンド数の減少が止まらない
経済産業省 資源エネルギー庁の統計によれば、ガソリンスタンド(給油所)数は1994年度末に約6万0421か所あったのをピークに、その後一貫して減少を続けています。
令和4年度末(2023年3月)時点で27,963か所となり、ピーク時の半数以下、実に30年でガソリンスタンド数は半減以下になりました。
特に地方や郊外での小規模スタンドの廃業が相次ぎ、「地域からスタンドが消える」といったニュースも珍しくありません。
また、事業者数(経営企業数)も平成元年(1989年)には3万2千社超ありましたが、令和4年度末には1万2754社と3分の1以下に減っています。
業界の担い手自体が減り、集約化が進んできたといえます。
なぜこれほどスタンドが減ったのか? 主な原因として以下のポイントが挙げられます:
- 燃費向上と需要減少
前述のとおり車の燃費性能が飛躍的に向上し、ガソリン消費量自体が構造的に減少傾向にあります。人口減や若者の車離れも重なり、国内ガソリン需要はピークを過ぎ右肩下がりです。需要縮小で採算悪化し、特に小規模なスタンドほど経営が厳しくなりました。 - 消防法改正による設備投資負担
2010年の消防法改正で、地下タンク等からの漏洩防止対策が強化されました。耐用年数40年を超える古い地下タンクは、防漏構造への改修か交換が義務付けられたのです。この対応には数千万円規模の費用がかかるため、老朽設備を抱えるスタンドの中には投資負担に耐えられず廃業を選ぶケースが多発しました。 - 経営者の高齢化・後継者不足
個人経営のガソリンスタンドでは、オーナーの高齢化に伴い後継ぎが見つからず閉店する例も増えています。「子供に継がせられない」「事業を売却しようにも買い手がつかない」といった悩みを抱える経営者も多く、高齢化と人手不足が業界衰退に拍車を掛けました。 - 業界再編と競争激化
国内の元売会社同士の合併(例:JXエネルギーと東燃ゼネラルの統合によるENEOS、出光興産と昭和シェルの経営統合など)で流通構造が変化し、生き残りを賭けた競争が激化しました。都市部を中心にセルフ式の大型店舗が増える一方、収益力で劣る地方の零細スタンドが淘汰される傾向が強まりました。
こうした要因が重なり、ガソリンスタンド業界は縮小の一途を辿っています。
「給油難民」という言葉が生まれるほど、一部地域では生活インフラとしてのスタンド維持が課題となっています。
生き残り策:サービスの多角化と新分野への転換
減少傾向が避けられない中で、生き残りを図るスタンドもあります。今後のガソリンスタンド経営の方向性として考えられているのは、主にサービスの多角化とEV時代への対応です。
- 油外収益へのシフト(サービスステーション化)
ガソリンそのものの販売以外で収益を上げるモデルです。具体的には、洗車、車検・整備、オイル交換やタイヤ販売など車関連のメンテナンスサービスを強化したり、店舗にコンビニやカフェを併設して集客するなどの取り組みです。
実際、灯油の宅配販売や、クリーニングの受け渡し、宅配便の取次ぎなど地域の暮らしを支える拠点として機能しているスタンドもあります。「ガソリンを入れるだけ」の場所から、車と暮らしの総合サービス拠点へと進化することで、燃料需要が減っても施設としての存在価値を維持しようという戦略です。
これにより一定の成功を収めているスタンドもあり、今後はより多様なサービス提供がカギになると予想されます。 - EV充電ステーションへの対応
将来のガソリン需要減を見据えて、電気自動車(EV)用の急速充電器を設置するスタンドも出始めています。
ただし課題もあります。EVの充電には時間がかかるため、わざわざ充電だけの目的でスタンドに立ち寄るケースはそれほど多くないと考えられています。
実際、現状では高速道路のサービスエリアやショッピングモール、道の駅など長時間滞在できる場所に充電スポットが設置される傾向があります。
またEVユーザーは自宅や職場で日常充電を済ませてしまうことが多く、スタンドが充電インフラに転換しても現在のガソリン販売ほどの集客は見込めない可能性があります。
したがって、EVステーションへの全面的な転換は慎重な検討が必要ですが、少なくともハイブリッド車向けの急速充電サービスやEV利用者の休憩施設として何らかの受け皿を用意する動きは今後増えるでしょう。
国としても2030年までに急速・普通充電器を約15万基整備する目標を掲げており、ガソリンスタンド跡地や空きスペースを活用した充電インフラ拡充が模索されています。
このように、需要減少という逆風の中でも知恵を絞ってビジネスモデルを転換しようとする取り組みが出てきています。ガソリンスタンド業界は今、まさに過渡期にあります。
何もしなければ衰退は避けられませんが、新たな役割を見出すことで地域に不可欠な存在として生き残る道もあるのです。
小規模事業者向け補助金の紹介~持続化補助金で経営強化~
ここで、ガソリンスタンドを含む小規模事業者の経営者にぜひ知っておいていただきたい補助金制度を紹介します。
それが「小規模事業者持続化補助金」です。これは中小企業庁などが管轄する、中小企業支援策の一つで、小規模事業者(要件を満たす従業員規模の小さい企業や個人事業主)が販路開拓や業務効率化の取り組みを行う際の経費の一部を補助してもらえる制度です。
- 対象となる事業者
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外)では常時使用する従業員が5名以下の事業者が対象になります(製造業その他は20名以下)。
ガソリンスタンドの場合、パートやアルバイトを除いた正社員が5人以下であれば該当します。まさに地方の家族経営的なスタンドや、小規模に運営している事業者はこの枠組みに入る可能性が高いでしょう。 - 補助内容
販路拡大や経営計画の実行に必要な経費の2/3(上限50万円~200万円)を補助してもらえます。
例えば、チラシ・ポスターの作成費用やホームページ作成費用といった広告宣伝費、新サービス告知のためのイベント開催費、古くなった店舗の一部改装費などが支援対象になります。
ガソリンスタンドで言えば、給油以外の商品・サービス(いわゆる「油外商品」)の販売強化のためのPRや設備改善などに充てることができます。
実際、この補助金は「ガソリンスタンドが抱える課題(客単価アップや既存事業の強化)を解決しやすい補助金」と評されており、大きな設備投資を伴わない範囲で現状打破を目指すのに適した制度です。
なお補助上限額は基本50万円ですが、条件次第では上限が100万円・200万円と引き上げられる特別枠もあり、最大で補助額200万円・補助率3/4まで拡充されるケースもあります。 - 申請と効果
持続化補助金を活用する際には、事業計画書(経営計画)の作成が必要になります。これは単なる補助金の申請書に留まらず、自社の強み・弱みや市場環境を分析し、中長期的な経営方針を整理する機会にもなります。
普段は目先の業務に追われがちな小規模事業者も、補助金の計画作成を通じて「自社を見つめ直し戦略を練る」プロセスを経験できるのです。
その意味でも、補助金の金額以上に得られるものが大きい制度と言えます。採択され補助金を得られれば資金面の助けとなるのはもちろん、計画策定を経て社内の目標共有や士気向上にも繋がったという声もあります。
※小規模事業者持続化補助金の詳細や具体的な活用事例については、当ブログの過去記事でも取り上げていますので、興味のある方はぜひ参考にしてください
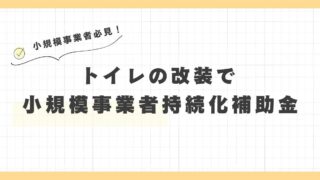

まとめ:業界の未来と経営者に求められる選択肢
最後に、本記事のポイントをまとめつつ、ガソリンスタンド業界の未来展望と経営者としての選択肢について考えてみましょう。
この20年、ガソリン価格は国際情勢に翻弄され、大きな波を描いてきました。中東やロシアの情勢悪化がある度に原油価格が急騰し、それが国内のガソリン価格にも跳ね返ってきました。
一方で、自動車の燃費向上によってユーザー側の燃料コスト負担は抑えられる傾向にあり、これはガソリン需要の構造的な減少を招いて業界にはマイナス要因となりました。
ガソリンスタンド数は激減し、業界は縮小フェーズに入っています。
しかし、だからといって「ガソリンスタンド=斜陽産業」と決めつけるのは早計です。確かに2030年代半ばには新車販売からガソリン車が事実上消えるという政策目標も示されており、長期的にガソリン需要が減っていくのは避けられません。
けれど、少なくともここ十年程度はハイブリッド車やガソリン車が主流であり続ける見通しで、すぐにガソリンスタンドが不要になるわけではありません。むしろ過渡期の今こそ、スタンドは地域に欠かせないインフラとしての役割を再定義し、p新たな価値を提供できる存在へ変革できるチャンスでもあります。
経営者としての選択肢としては、大きく分けて二つの方向性が考えられます。
- 現行ビジネスの延長線上で効率化・多角化する道
つまり、今のガソリン販売を核とした業態をベースに、サービス拡充や経営効率化で収益を確保しつつ、需要減の中でも生き残る戦略です。
具体的には前述したような洗車・整備サービスの強化や、地域密着型の顧客サービス(高齢者への給油代行やモバイルオーダー対応など)の導入も考えられます。
また、自治体や他業種と連携し、防災拠点・物流拠点としての役割を持たせるなど、「エネルギーステーション+α」への転身も一案です。
この路線を進める上では、小規模事業者持続化補助金をはじめとする支援策を上手に活用し、限られたリソースで効果的な投資・PRを行うことが重要になります。 - 思い切った事業転換・撤退も視野に入れる道
もう一つは、長期的なガソリン需要の先細りを見据えて業態転換を図る決断です。例えば、給油所からEV充電インフラやカーシェア拠点への転換、あるいは全く異なる事業へのピボットも選択肢として考えられます。
実際、事業再構築補助金などを使ってEV関連設備に投資したり、新業態に挑戦した例も出始めています。
もちろん長年培った顧客基盤やロケーションの強みは活かしつつ、新しい収益源を模索する必要があります。
また、高齢で後継者がいない場合などは、無理に事業を続けて体力を消耗するよりも、早めに廃業や売却を検討しソフトランディングを図ることも一つの勇気ある選択です。地域の他事業者との合併・統合による生産性向上も、今後検討されるかもしれません。
いずれの道を選ぶにせよ、重要なのは情報収集と計画的な対応です。補助金や業界動向の情報にアンテナを張り、使える支援策は遠慮なく使いながら、自社の強みを伸ばし弱みを補う戦略を描く必要があると思います。
幸い、本記事で見たようにガソリン価格や燃料費の動向データ、政府の支援制度など、経営判断の材料は揃いつつあります。あとは経営者の皆さんが将来を見据えて舵を切る番です。
まとめとなりますが、ガソリン価格は今後も国際情勢によって上下し得ます。ただ、日本政府の政策やエネルギー転換の流れから考えると、「高騰すれば補助で抑える」「徐々に税制や構造でソフトランディングを図る」方向で推移するでしょう。
ガソリンスタンド業界自体も、小規模事業者に対する補助や支援策を活用しながら、時代に合わせて変化していくことが求められています。業界の未来は決して楽観できるものではありませんが、「ピンチをチャンス」に変える発想で、地域に愛され選ばれるスタンドづくりに挑戦していきましょう。
本記事の情報が、皆さんの経営判断の一助になれば幸いです。
(参考資料)
国際情勢と原油価格の関係bloomberg.co.jprieti.go.jp
政府のガソリン補助金政策moneycanvas.bk.mufg.jpenegaeru.com
ガソリン価格と燃費の長期推移データenegaeru.comontheroad.toyotires.jp
ガソリンスタンド数の推移と業界動向nttev.comnttev.com
小規模事業者持続化補助金の概要roadsidekeiei.compalette-tech.com